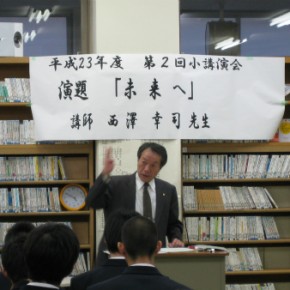Category Archives: 図書館イベント
小講演会「シルクロードから見た日本~古代七つの文明展を終えて~」(谷一尚氏)(’12.7.13)

去る7月13日(金)、図書委員会主催第1回小講演会が図書館で開かれました。今年度は岡山市立オリエント美術館館長の谷一尚氏をお招きし、「シルクロードから見た日本~古代七つの文明展を終えて~」と題して講演をいただきました。生徒・教員をあわせ、40人ほどが参加しました。
お話は、シルクロードとは何かということから始まりました。広い意味でユーラシア大陸における東西交易路の総称であり、先生は117回、74か国に及ぶ現地調査をされ、さまざまな遺跡発掘経験を持たれていました。たくさんの写真を交えて、先生の体験を紹介して下さいました。
また、日本とシルクロードとの関わりについて、正倉院の宝物とシルクロードで発掘された品々との共通点を挙げて分かりやすく説明して下さいました。連珠文という模様はその一例で、シルクロードがいかに日本に影響を与えていたかも知ることができました。
先生は、「生活」と「物」との関係についても触れられました。杯の形を例に、人の生活形態が物の形にも影響を与えることを教えて下さいました。「乾杯」という言葉があるように、注いだお酒は飲みほしてしまうもの。このため、杯は置くことができない形になっているということでした。
シルクロードと日本だけでなく、人々の生活と物の関係に至るまで、ユーモアを交えながら話して下さり、非常に興味深いお話を聞くことができました。生徒たちも古代の世界と日本の関わりに興味を持ち、視野を広げることができたと思います。
読書会(’12.6.15)

6月15日(金)に図書館で1・2年図書委員による読書会が行われました。取り上げた作品は、重松清の「千代に八千代に」です。
4グループに分かれて感想を述べ合った後、まとめを代表者が発表しました。他グループの発表を聞くことで、新しい視点に気付かされることもあったようです。また、作品の疑問点について議論を重ね、さらには「何故この題名なのか」というテーマに挑戦。
活発な意見交換が繰り広げられ、大変充実した読書会になりました。
子ども読書の日フェスティバル(’12.4.21)

4月23日の「子ども読書の日」にあわせ、4月21日(土)に岡山市立南公民館で「子ども読書の日フェスティバル」が開かれました。
当日は幼児から小学生、中学生、高校生、大人まで81名が集まりました。
参加した9名の高校生たちは、絵本を読み聞かせたり、バイオリンの演奏に合わせて童謡を皆で歌ったりし、会を盛り上げてくれました。
図書館オリエンテーション(’12.4.11)

4月12日(水)、1年次生を対象にした図書館オリエンテーションを行いました。
司書教諭と司書が図書館活用の意義・利用案内・おすすめの本などについて語りました。
資料として「図書館利用の手引き」「図書館利用案内」「高校生の、君が主人公」を配布し、「1年次生は4月中に最低一冊は貸出もしくは予約をしましょう」と呼びかけました。
どきどき・わくわくブックワールド2012(’12.1.28)

1月28日(土)10時~12時、お隣の岡山市立南公民館で「どきどき・わくわくブックワールド2012」が開かれました。
本校からは高校生有志4名が参加し、地域の子ども達に絵本を読み聞かせたり、一緒に工作やカルタを楽しんだりして交流を深めました。
HR読書会(’11.11.7)
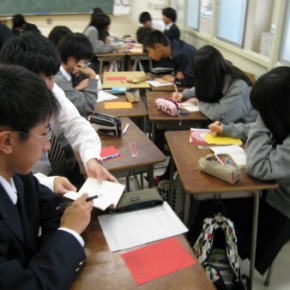
秋の読書会はクラスごとに行います。 1・2年次生とも、11月7日(月)のLHRの時間に行いました。
今回は、新しい取り組みとして保健委員会とのコラボレーション(眼のリラックス体操)、コメントカードの作成・校内展示を実施しました。
夏休みフリー塾(’11.8.5)

8月5日(金)10:00~12:00、本校図書館で小学生対象の「夏休みフリー塾」を開催しました。
本校からは高校生有志18名が参加し、当日は地域の小学生48人に加え、岡山南公民館館長さんと芳泉・浦安子ども劇場の方、世話役のお母さん方が来校してくださいました。
公民館館長さんと図書委員長の挨拶のあと、『ぼちぼちいこか』(マイク・セイラー、ロバート・グロスマン)、『おまえうまそうだな』(宮西達也)の2冊を有志生徒と演劇部が読み聞かせ、子どもたちを絵本の世界に引き込んでいました。それに続く宿題お手伝いの時間では、グループごとに分かれたそれぞれの机から楽しそうな会話や笑いが絶えず、お互い勉強だけにとどまらない楽しい時間となりました。最後に行われた有志生徒による絵本の読み聞かせ『ねえ、どれがいい?』では、選択肢が現れる度に子どもたちから「こっちがいい!」「あっちはイヤ!」「こっち!だってね、……」といった声が続々と上がり、大いに盛り上がりました。
お開きの後はお互いに名残を惜しむ様子が見られ、地域や異年齢間の交流は、高校生にとっても自身の学び・成長の機会となったようです。